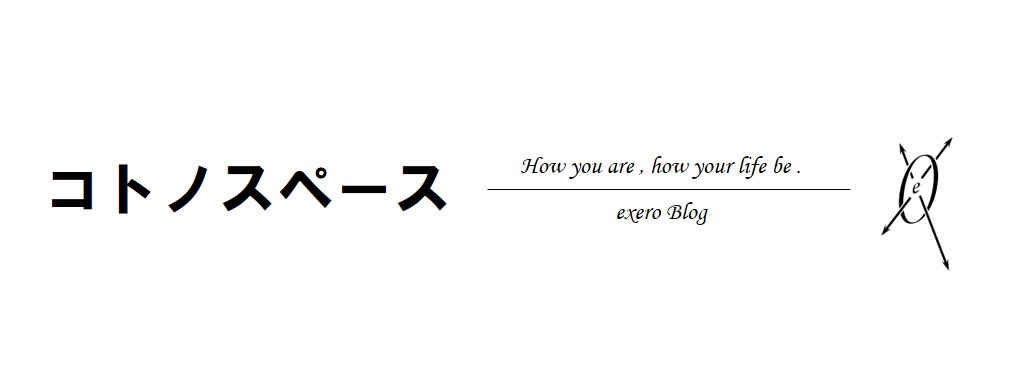その森には、大きな大きな巨木が
何本もそそり立っていた。
森に住む妖精たちは、
たくさんの巨木のまわりを飛び回り、
「もっと幸せになれますように!」
と、口々に願いを言い続けた。
妖精たちは、もっと幸せになりたかった。
そして、どの妖精も、巨木のどれかが
自分を幸せに導いてくれるだろうということを
信じて疑っていなかった。
春。
巨木たちは、たくさんの花で
自らを華やかに飾った。
赤、青、黄、ピンク。
色とりどりの花は、
見ているだけで妖精たちを幸せな気持ちにさせた。
「この花が、私を幸せにしてくれるに違いない」
ほとんどの妖精は確信し、
巨木がもたらした花を手に取り、
自らを着飾っていった。
しかし、巨木からむしり取られた花は
数日経つとしおれて、色あせてしまっていった。
花を身につけた妖精たちは
一時的には幸せな気持ちになるものの、
自分たちが望んでいるような幸せにはたどり着けなかった。
なので、ほとんどの妖精たちは、
「これは、手に取った花が悪かったんだ」
「もっと別の、もっと華やかな花を手に入れれば
きっと幸せになれるはず」
と、我を争うように新しく咲く花を追い求めていった。
ただ。
他の妖精の動きを離れて見ていた
一匹の変わり者の妖精は、
「花には、ぼくの幸せはないな」
と思い、巨木をじっと眺めていた。
夏。
巨木は、青々と茂った葉を揺らせていた。
ほとんどの妖精たちは、夏になると、
「どうやら、花は幸せをもたらしてくれなさそうだ」
と口々に言い始めた。
そして、巨木の葉をお世話することにした。
巨木の葉を食べに来ようとする虫たちを追い払い、
巨木に、
「ぼくが一番、あなたのために働いています」
と、みんながアピールをするようになった。
ほとんどの妖精は、自分のお気に入りの巨木を見つけると
「ぼくがお世話している、
この木が一番立派で正しいんだ!」
「いやいや、君の好きな木なんか、ニセモノさ。
やっぱり、ぼくがお世話している木が一番さ!」
と、ののしりあうようになった。
巨木は、妖精たちの存在を知ってか知らずか、
ただ黙って葉をゆらせている。
ほとんどの妖精がののしり合っている中、
変わり者の妖精はただ一匹
「ぼくの幸せは、葉っぱにもないな」
と、ただただ巨木を眺めていた。
秋。
巨木たちは、いっせいに果実を実らせ始めた。
実らせる果実は、巨木によって違ったけれど、
それぞれが魅力的な果実だった。
夏の頃にお世話をしていた葉が枯れ落ちるのを見ると、
ほとんどの妖精たちは
「この果実こそが、ぼくが追い求めていたものだ!」
と、我先にと、果実をほうばって行った。
ほとんどの妖精たちは、
「これは、ぼくが夏にお世話をしたからできた果実だ。
君たちにはあげないよ」
と、果実を独り占めしようとがんばっていた。
ただ一人、変わり者の妖精は、
「花が咲き、葉をつけ、果実が実る。。。
この地面の下で、巨木たちは、どんなことをしているのだろう?」
と、変わり者らしいことを考え始め、
巨木の幹を丹念になで、地面の底にある根っこに
思いをはせた、
そして、冬。
木枯らしが吹き、巨木たちの枝には
花も、葉も、果実もなくなっていた。
ほとんどの妖精たちは
「あーあ、やっぱりここにも
ぼくの幸せはなかったんだ」
「そんなことだろうと思っていたよ。
だから、だまされちゃダメだって言っただろう?」
と口々に言いながら、
巨木のもとを去って行った。
「南の方に、新しい花を咲かせた木があるってさ!」
そんな噂がどこからともなく広まり、
妖精たちは我先にと、新しい花があると言われた場所を目指して
飛び立っていってしまった。
ただ一人、変わり者の妖精は、
「枝の先には、花も、葉も、果実もない。
でも、感じるぞ。
地面の下で、命が動いているのを」
と、木の幹、そして地面に耳を当てていた。
すると。
目の前に、ひとつぶの種が落ちているのを見つけた。
地面の下で、何が起こっているのを
すべて見ることはできない。
なら、1から種を育ててみることで、
地面の下で起こっている事を感じてみよう。
変わり者の妖精は、ひとつぶの種を地面に埋め、
自分の木を育ててみることにした。
厳しい冬を越し、春がやってきた。
ほとんどの妖精たちは、また森へと戻ってきた。
「やっぱり、あそこにも
ぼくたちの幸せなんか、なかった」
「見て!去年よりも立派な花が咲いているよ!
やっぱり、花がぼくを幸せにしてくれるんだ!」
ほとんどの妖精たちは、
1年前と同じように、我を争って花で着飾り始めた。
変わり者の妖精は、
もう他の妖精たちが何をしていようが、
気にとめることすらなくなった。
枝の先につく花も、葉も、果実も、
自分を幸せにすることはないことが
確信できたからだった。
春が終わり、夏が来て、秋になり、また冬が巡る。
ほとんどの妖精たちは、
その時その時に巨木についたものに反応し、
「これこそが、ぼくを幸せにしてくれる」
と言っては、
「やっぱり、違ったな」
と落胆する。
でも、変わり者の妖精は、巡る四季の中で、
我を忘れて、自分の木を育て続けた。
まるで、自分が育てている木と
一体にでもなるかのように。
そして。
あれからどれくらいの季節が巡っただろう?
また春が訪れた。
「あ!あの木の花、とっても綺麗だ!」
たくさんの妖精たちの一匹が、めざとく見つけた。
変わり者の妖精は、自分に向かって妖精が飛んでくるのを
不思議に思った。
むらがるように、たくさんの妖精が
変わり者の妖精に向かってくる。
そう。
いつのまにか、変わり者の妖精は、
巨木の1本になっていたのだ。
巨木になった変わり者の妖精は、
自分がいつのまに巨木になっていたのかに驚いたが、
「そんなことは、どうでもいいか」
と思うようになっていった。
春、変わり者の妖精だった巨木は、花を咲かせる。
夏には、葉を茂らせる。
秋には、自分の果実を実らせ、
そして冬には、木枯らしに抱かれながら根を張る。
変わり者の妖精だった巨木は、
もう他の妖精たちと話すことはできなくなっていた。
でも、他の妖精たちが周りを飛び回ってくれることに
幸せを感じていた。
そして。
いつの日か、できることなら
以前のぼくと同じような
変わり者の妖精が現れて、
ぼくの仲間になってくれたらいいな。
そんなことを思いながら、
繰り返す四季に抱かれ続けていった。