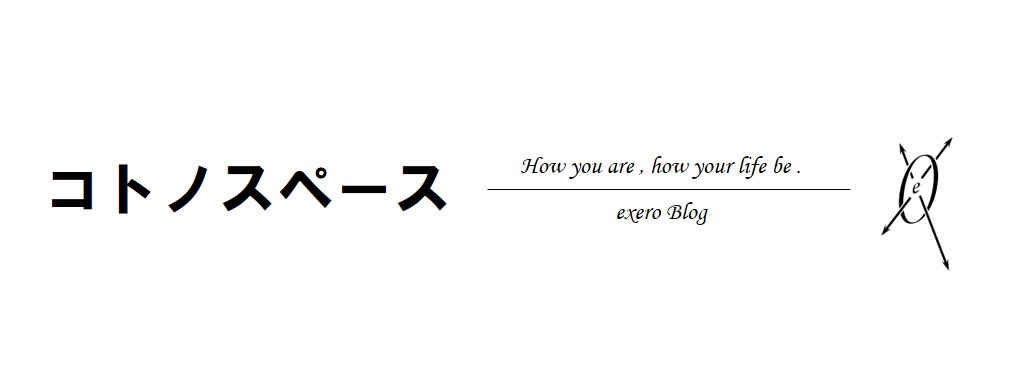もう、10年以上会ってない友人から
一通の手紙が届いた。
「お互いに仕事も ひと段落しただろうから、
会って思い出話でもしようじゃないか」
そんな内容だった。
たしかに、だいぶ仕事も落ち着いてきた。
ここらで、長めの休みを取って
彼に会いに行くのもいいかもしれない。
彼は現在、「理想的な都市」として有名な
ある街に住んでいた。
私はどのような都市なのか、まるで知らなかったが
とても豊かで安全な街のため、
世界中のリッチな人々が、こぞって集まっているらしい。
ものはためし、
ということで、私は彼の誘いに応じ、
その「理想的な都市」に遊びに行くことにした。
—
「やあ!こっちこっち!」
空港で待っていてくれた彼は
私に会うなり、陽気に手を振ってくれた。
「ようこそ!理想的な都市へ!」
彼は仕事で大成功し、
巨万の富を手に入れ、この都市に住んでいる。
立ち振る舞いもスマートだし、
充実した生活を送っているようだ。
「ここは、住みやすいんだってね」
私がそう尋ねると、彼はよくぞ聞いてくれたというように
「そうなんだ!
ここは、なんと犯罪件数0件、
みんなが親切で、ゴミも1つも落ちていない」
と説明した。
周りを見てみると、
たしかにゴミは全く落ちていないし、
街ゆく人々は、みんな微笑んでいる。
「さぁ、ここからは車で移動しよう」
彼は停めておいた自分の車に
私を乗せると、アクセルを思いきりふかして
走り出した。
「おいおい、これって
スピード違反にならないのか?」
彼があまりにもスピードを出すので、
私は恐る恐る聞いてみたが、彼は
「それは、大丈夫なんだ」
と、さらにグッとアクセルを深く踏み込んだ。
—
彼の巨大な邸宅に着くと、
彼が雇っているメイドさんが
ニコニコとお茶を出してくれた。
街ゆく人々と同じで、とても愛想がいい。
「しかし…」
なんだろう?この、どことない違和感は。
「さあ、会って話すのは何年ぶりだろうな、、、
君は、どうしていたんだい?」
と彼は私に話を向けたが、
しゃべりだすと、彼自身がどのように
成功していったのか?という自慢話が
ほとんどだった。
「お金があれば、この世は天国だ」
彼は話の途中で何回もこのフレーズを口にし、
自分が「勝者」であることに酔いしれているようだった。
ひとしきり彼の話が終わった後で、
私は聞いてみた。
「ところで、会った時に
この都市は犯罪がゼロ件と言っていたけれど、
そんなことって可能なのか?」
彼は、ああそんなことか、といった表情で、
「もちろんさ。
この街に住んでいる人の周りには、
24時間、つきっきりで監視カメラがついているからな」
と私に言った。
「監視カメラ?」
「ああ。もちろん君にも空港に着いた時から
目に見えない監視カメラが、君の周りを飛んでいる。
だいたい、1人につき7~8個は
飛び回っているんじゃないかな?」
彼の言葉を聞き、私は周りに目を凝らしてみたが、
カメラはまったく見えなかった。
そんな私の態度に軽く笑いながら
「そんな簡単に見えるような、チンケなカメラじゃないよ。
ものすごく小さい、ハウスダストよりも小さな
高性能カメラなんだ。
そのカメラたちが、朝から晩まで、
もちろん眠っている時もトイレにいる時も
ずっと一人一人を監視している。
だから、泥棒なんてする人はいないし、
他の犯罪も、やった途端に捕まるんだから
割に合わなくて、誰もやったりはしない」
と、目の前のコーヒーに口をつけた。
「でも、さっき君は、
とんでもないスピードで車を飛ばしていたけれど
あれは大丈夫なのかい?
それこそ、監視カメラで見られているだろう?」
私はなんとも言えない閉塞感を感じながら
彼に聞いてみた。
「ああ、あれはもちろん、交通違反だ。
ただ、この街では、
交通違反は罰金を支払う以外の
ペナルティはないんだ」
と彼は言うと、ポケットに入れていた
携帯端末の画面を私に見せた。
「ほら、さっきの罰金がもう支払われている。
罰金以外のペナルティがない、ということは、
つまりお金を払えば、どんな運転をしてもいい、
ってことなんだよ」
そこに表示されている罰金は、
さきほどの短時間のドライブだけで
普通の人の月収以上の金額になっていた。
「この街は、交通違反も
ひとつのビジネスなのさ」
と、彼はむしろ「自分はビジネスに貢献している」
とでも言わんばかりに、うそぶいた。
「もちろん、貧乏な人もこの街で働いている。
うちで雇っているメイドみたいにね。
彼ら彼女らは、実家に仕送りするために
自ら進んでこの街に住んでいるんだ」
「そして彼らの行動や表情は
常にカメラとAIで評価されている。
だから、みんな愛想いいだろ?
これが、この街をさらに住みやすくしているのさ」
—
「もう帰るのかい?
もっとゆっくりして行けばいいのに」
彼は引き留めてくれたが、私は予定を早めて
帰ることにした。
彼は、なにかピンと来たらしく、
「ははぁん!大丈夫だ。お金のことなら心配するな。
昔からの友達である君の財布なんか
あてにしていないよ」
と、さわやかに笑ったが、
私の気持ちが変わることはなかった。
—
私は帰宅した。
まだ監視カメラがついているんじゃないかと
気になったが、どうやらそれは解除されるらしい。
「おかえりー!」
「あの町はどうだった?」
「美味しいものばっかり食べてきたんじゃない?」
仲間がワイワイと出迎えてくれた。
考えてみると、あの都市に住んでいる彼のまわりには、
メイドさんくらいしかいなかったな。
彼の話の中でも、ビジネスで付き合っている人や、
お金が介在している人しか出てこなかった。
「あいつは使える、使えない」
「あのモデルは、いつも俺にすり寄ってくる」
そんな話ばかりだった。
「理想的な都市、か…」
私の周りには、笑い合える仲間がいる。
ぜいたくじゃなかったとしても、
食べるものも、着る服も、住む場所もある。
たぶん、監視なんかしなくても、
家の鍵をかけ忘れても、誰も悪いことなんかしない。
誰かが困っていたら、普通に助ける。
私は財布を置いて、仲間のもとに走って行った。