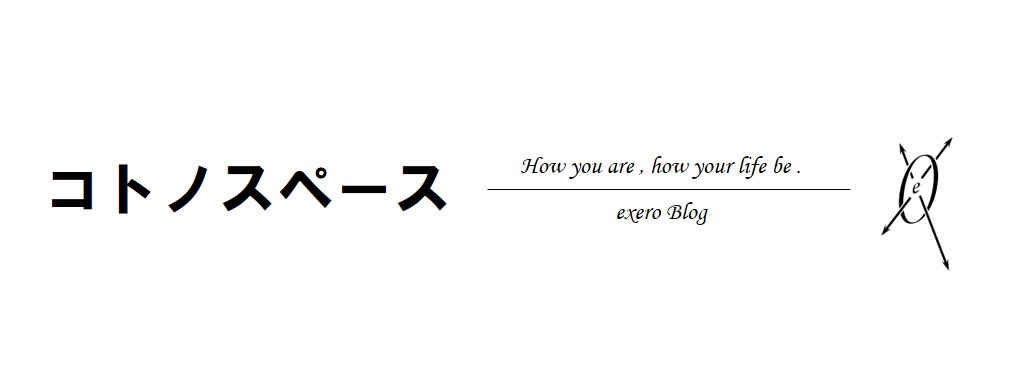継母は、いつものように朝一番に起きて
こっそりと、暖炉の中の灰に魔法の粉をまぜた。
「あと3日、、、ですわ、、、」
継母は、今までやってきたことが水泡に帰さないよう
今まで以上に慎重に計画を進めていこうと
決意を新たにした。
彼女が起きてくる前に、
もう一度ベッドに戻り、さも遅くまで寝ていたように
ふるまわなければならない。
「おはようございます、お義母さま」
彼女は朝から、せっせと働いている。
継母にとって、彼女に冷たく当たるのは
心がちぎれてしまうほど辛いことであったが、
これも将来の彼女が王宮で過ごす時に
きっと必要な経験になってくるはずだ。
少なくとも、継母自身には
その確信があった。
継母は彼女のあいさつには応えず、
「ほら、ここがまだ汚れていますよ」
と、いつものように彼女の仕事ぶりを
なじった。
そうしているうちに、2人の義姉も
リビングへとやってきて、彼女に用事を言いつけ始めた。
いつもの光景。
心を鬼にしてやっているものの、
継母にとっては、つらいつらい毎日の連続だった。
そして。
とうとう舞踏会の当日がやってきた。
一日千秋、という言葉が
これほど当てはまることはないだろう、
と、継母は今までのつらい日々を振り返った。
彼女に対しては、今までの仕打ちを
謝りたい気持ちでいっぱいだった。
しかし、それでは悪役を全うできない。
自分に課した役割を、最後まで果たすために、
継母は、
「早くドレスを持ってきなさい」
と、自分と姉2人が着るためのドレスを
彼女に持ってこさせるのだった。
—
「ここからが、本番ですわ」
と、継母は舞踏会の会場から引き返してくると、
前々から準備をしていた隠れ家に入った。
隠れ家に入ると、一刻も無駄にはできない、と
用意をしておいた魔法使いのフードを着、
杖を手に取った。
「あとは、彼女にかぶらせていた
魔法の粉が効いてくれれば。。。」
と、毎朝、灰の中に忍ばせておいた魔法の粉が、
彼女にいつも以上の輝ける美貌と、
ダンスのセンスを与えてくれることを祈った。
そして最後に、
隠れ家の棚の一番奥にしまってあった
袋を手に取った。
その袋の中に入ったガラスの靴を取り出し、
愛おしむように、そっと撫でてみる。
「がんばってね。。。」
継母はひと言だけそういうと、
彼女の待つ自宅へと急いだ。
—
「まさか、、、こんなことって、、、」
魔法によって、彼女は輝くように美しく彩られた。
そばには、すぐにでも出発できるように、
かぼちゃの馬車が彼女が乗り込むのを
待っている。
彼女は、まぶたにいっぱい嬉し涙をためて、
魔法使いに扮した継母に
最大限のお礼を言った。
(よかった、彼女には、見破られていないようだわ)
継母は、夢見心地になっている彼女に
気づかれないように、フードを深くかぶりなおした。
「さあ、早くお行き!
12時の鐘が鳴ってしまったら、
魔法は解けてしまうのだから」
魔法使いとなった継母は、
彼女をせかす。
彼女はピカピカのガラスの靴を履き、
踊るように、かぼちゃの馬車に乗り込んだ。
「ありがとう!魔法使いさん!
必ず12時前には、ここに戻ってくるわ!」
と言って手を振る彼女を、
魔法使いである継母は見送った。
彼女が12時にここに戻ってくるどころか、
彼女が12時ギリギリまで王子と踊ってしまうことを
知りながら。
—
舞踏会は終わり、またいつもの日常が始まった。
今の彼女にとっては、舞踏会は
もう終わってしまった最良の思い出なのだろう。
しかし、彼女はもう少ししたら気が付くだろう。
舞踏会は、これからの人生の
スタートだったのだ、ということを。
継母は、城からのお迎えが来るまで、
気持ちを引き締めて、彼女に冷たく当たった。
これが、彼女にしてあげられる
最後のプレゼントなのだ、ということを
かみしめながら。
「ごめんください。城から参りました」
とうとう、使者がやってきた。
継母は、それからのことはあまり覚えていなかった。
ただ、彼女が恐る恐るガラスの靴を履き、
それがぴたりとおさまった瞬間の
彼女のあふれる笑顔だけは、
涙でくもる景色の中でも、鮮明だったように思う。
—
「さて」
城からのお迎えの馬車に乗り込んだ彼女を見送ると、
継母は、最後の仕事にとりかかった。
2人の姉に、杖をひと振りする。
すると、今まで人間であった2人は、
たちまち2匹のネズミに戻ってしまった。
ネズミの体には、灰のような魔法の粉が
たっぷりとかけられていた。
「お前たち、長い間、
大変な役目を果たしてくれたね。
本当にありがとう。
もう、つらい思いをさせないからね」
継母であった女性は、
ネズミを優しくなでると、
「さあ、帰りましょう」
と言って、杖をもうひと振りした。
すると、なにもない空間に、光り輝く扉が現れた。
継母であり、魔法使いでもあった女性は、
少し名残惜しそうに自宅の方を見たあと、
魔法の扉を開けて、中に進んで行った。
—
「女王、本日もごきげん麗しゅう」
「本日は、ずっと自室におこもりのご様子でしたが
ご不便はございませんでしたか?」
家臣が敬意をもって女性にかしづく。
継母であった女性にとっては、ここに戻ってくるのは
数年来の帰還なのだが、
他の人たちにとっては、たった一日に過ぎなかった。
女王と呼ばれた、継母でもあり魔法使いでもあった
女性は、家臣たちに優しい微笑みを浮かべる。
きっと、若い頃の苦労がなければ、
こんなに家臣たちに優しくできなかっただろうし、
家臣たちの気持ちもわからなかっただろうな、
と、ふと思う。
そこに、女性の夫である王が帰ってきた。
「おかえりなさいませ」
「ああ、ただいま。
君は今日も、魔法の勉強だったのかい?」
女性は王の問いかけに、微笑みを返した。
「結婚をした時には、まさか君が
わが国の中でも一、二を争うほどの
魔法使いになるとは、思ってもみなかったよ」
と言いながら、王は妻である女王に
軽くキスをした。
女王は言った。
「ええ、私も。
でも、そのおかげで、私はあなたと
こうやって幸せになっているのです」
王は、その言葉の意味を図りかねていたが、
ふと気づいて女王に聞いた。
「おや、君の部屋に飾ってあったガラスの靴が
ないようだが。。。?」
女王は答えた。
「あれは、大切な人に出会いたいと願う
若い女性にお譲りしましたわ。
あの靴を履けるのは、彼女以外おりませんから」
王はまた、彼女が何を言っているか
その意味のすべてが理解したわけではなかった。
しかし、それはどうでもいいことだ。
私は、彼女を愛しているのだから。
王は、女王の手を取って
いつもの玉座に向かう。
「さあ、行こうか。シンデレラ」