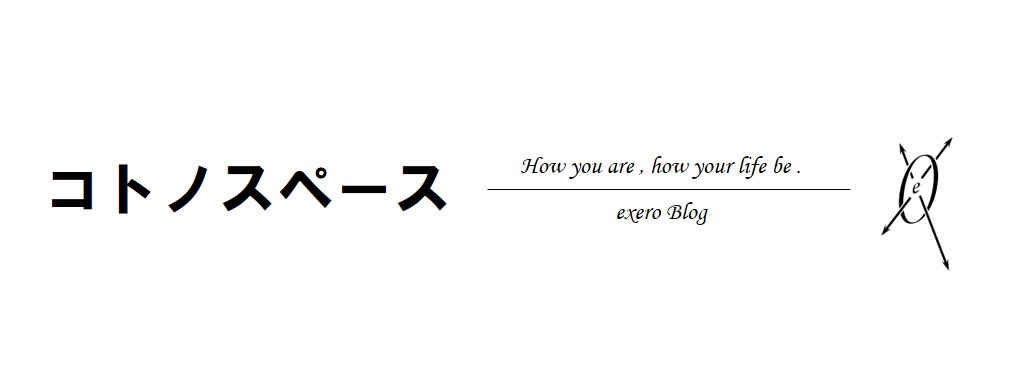もう僕は、外の景色を見る事はないだろう。
それどころか、この手術台から見える
まぶしいライトが、僕が見る最後の景色になりそうだ。
寝ている僕のまわりでは、何人ものお医者さんや看護師さんが
僕をなんとか生き長らえさせようと
懸命にやりとりをしてくれている。
パパやママもそばにいてくれているみたいだけれど、
もう意識がぼんやりとしていて、
誰が何を言っているのかも、僕には分からない。
僕にはただ、心拍が続いていることを知らせる緑色の光が
一定の間隔で波打っているのを
まるで他人事のように見ているのが精いっぱいだった。
僕は、生まれた時からずっと身体が弱かった。
ちょっと走るだけでも心臓がドキドキして、
すぐに息切れをしちゃう。
生まれつき、どうも心臓が弱いらしくて
なにかあるとすぐに病院に入院して、
また恐る恐る退院するという日々の繰り返しだった。
僕をこんな弱い身体に生んでしまったことを
ママは何回も謝ってくれたけれど、
そんなのママのせいじゃないことは分かってる。
僕にとって、この身体でいることが普通なんだから、
ママはそんなに自分を責めないで欲しいな。
ただ、もっと色んな人に出会って、
色んな事をしたかったな、とは思うけれどね。
—
手術室は、いよいよ緊迫感を増してきて、
僕に、ありとあらゆる延命措置がとられているみたいだった。
そりゃ、僕だって生きられるのなら生き続けたい。
でも、そこまで一生懸命やってくれてダメだったんなら、
もう仕方ないかな、なんて風にも思う。
一定のリズムで波打つ緑色の光は、
次第に弱々しくなり、その頻度も頼りなげになってきていた。
そして。
ピー、という音とともに、
波打つことをやめた緑色の光が、
僕がこの世で見た最後の光景となった。
僕の意識は手術台から離れ、どんどんと宙に登ってゆき、
お医者さんたちの声が遠ざかってゆく。
病院の天井を超え、空高く浮遊してゆくと、
あたりが急に暗くなりはじめ、
意識が遠のくような感覚に見舞われた。
次に気がつくと、
僕はなぜか、いつのまにか映画館の中にいた。
「ここは。。。?」
あたりを見回すと、映画館の中には僕だけしかいないようで、
後ろを振り向くと、ひとすじの光が
カシャカシャと回る映写機から伸びていた。
スクリーンに向き直ってみると、画面の真ん中には、
「Fin」
と、映画が終わったことを示す文字が浮かび、
その後には、静かな音楽とともに
下から上へと、白い文字が流れていっていた。
よくある、映画が終わったあとのスタッフロールだ。
でも、たしか僕は死んだはず。
なんで、映画館になんているんだろう?
不思議に思いながら、ふとスクリーンを見ると
そのスタッフロールに、ある違和感を覚えた。
「あれ?ここに名前が出てくる人たちって。。。」
スタッフロールに現れる名前をよく見ると
どの名前も、僕の知っている人ばかりだ。
僕の親友の名前が出たかと思うと、名前のあとには
「大切な友達」と、カッコつきで表示されている。
友達だけじゃなくて、学校の先生の名前も出て来るし、
保険の先生の名前も出てくる。
そうかと思うと、ずっと僕を診てくれていたお医者さんの名前も、
下から上に流れるスタッフロールに現れてきた。
「これって、もしかして。。。?」
その後も延々と続くスタッフロールをみて、
僕は直感的に悟った。
これは、「僕の人生」という物語の
スタッフロールなんだ!
今、僕が死んでしまったことによって
僕自身が関わってきた人たちの名前が
走馬灯のように映し出されているんだ。きっと。
次々と現れる名前に、僕は思わず涙ぐんだ。
むかし、よく遊んでいた近所の友達。
近所のスーパーで働いていたおばちゃん。
自分の犬をなでさせてくれたおじちゃん。
他の人と比べて、僕の生涯はそんなに長くはなかっただろう。
それでも、こんなにたくさんの人と出会い、
僕を支えてくれていたんだ。
ごめんなさい、なにもお返しできなくて。
一人一人に、ありがとうを言いたかった。
でも、それももう手遅れだった。
流れ続けるスタッフロールは、
どんどんと僕が知らない名前が増えてきた。
日本人の名前だけじゃなく、外国人の人もいた。
中には、なんて読めばいいのかもわからない人たちも。
ただ、名前の後ろに続くカッコ書きのおかげで、
どんな風に僕に関わってくれたのかは分かった。
僕が大切だったおもちゃを作ってくれた人。
食べ物を作ってくれた人。届けてくれた人。
絵本を書いてくれていた人。
その本の紙を作ってくれた人。
本当に、本当に、いろんな人が僕に関わってくれていた。
生きている間、僕はそんなこと
全然気にもしていなかった。
でも、こんなにも僕に関わってくれていたんだ。
長い長いスタッフロールが続き、
カッコ書きに「ご先祖さま」が現れてきた。
そっか。そうだよね。
僕が生まれてきたのは、ご先祖さまがいてくれたからだよね。
果てしなく続く名前を見つめ続けていたけれど、
不思議と疲れはなかったし、時間の経過自体も
生きていたころの感覚とは違うみたいだった。
そして。
永遠に続くかと思われたスタッフロールも
最後の時が来たようだった。
おじいちゃんやおばあちゃんの名前が現れ、
そして間をあけて、パパとママの名前が現れた。
パパとママの名前が一番上まで流れてゆくと、
しばらく真っ黒な画面が続くと、
スクリーンの幕が静かに降りてきて
場内が明るくなり始めた。
一人一人にお礼を言うことはできなかったけれど、
最後の最後に、みんなを思い出せてよかった。
ありがとう。
明るくなった場内は、さらに強い光に包まれてゆく。
「ああ、たぶん、僕はこのまま、いくんだな」
そんな事を思いながら、僕は柔らかくも力強い光に
抱かれていった。
さようなら。ありがとう。
—
と。
今までの強い光が、しだいに弱まってゆく。
そして、映画館の椅子や幕が見られるほどに光は薄らぎ、
さらに暗くなってゆく。
僕がその変化に驚いていると、
スクリーンの幕が再びスルスルと上がり、
後ろでは、映写機がまたカタカタと回り始めた。
僕が仕方なくもう一度座席に座ると、
追加された、たった一人のスタッフロールが表示された。
ある男性の名前が最後に表示され、そこには
「心臓提供者」
という文字が書かれていた。
それを確認すると同時に、
僕の意識は遠くなった。
—
「退院おめでとう。
間一髪で、心臓のドナーさんが現れて、
移植手術に成功して、本当に良かった」
退院の日、お医者さんは僕に
そんな優しい言葉をかけてくれた。
「先生、ずっと気になっていたんですけれど、
僕に心臓を提供してくれた人の名前は。。。」
と僕が言いかけると、お医者さんは
「それは、ルールで教えられない事になっているんだ」
と言葉をさえぎった。
でも僕はそれに構わず、ある名前を口にした。
それはもちろん、スタッフロールに映し出された名前だった。
お医者さんは僕の言葉を聞くと
「なぜ、それを。。。?」
と驚くような顔をした後、優しい目で僕に微笑んでくれた。
「預かった命、大切にするんだよ」
僕は、これからもたくさんの人たちに支えられて
生きて行くんだろう。
そして、僕も誰かの「スタッフロール」に書かれるように
がんばって生きて行く。
だって、きっとそれが、奇跡の連続で出来ている
この世界に生きている意味なのだろうから。ね。