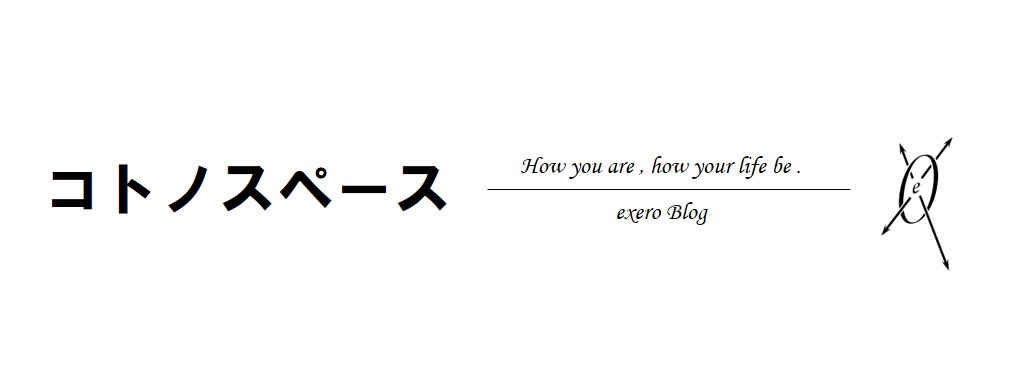「フレンドロイド」。
現在では、
「人間と寸分も違わない
アンドロイドの友達がいない」
という方が珍しいくらい、
友達型アンドロイドは普及していた。
はじめのアンドロイドは、
子供たちが危険な目に合わないように
警護するのが主な役割であったが、
フレンドロイド各社の競争により、
「より子供たちに愛されるアンドロイドを」
という研究の蓄積が、子供たちにとって
最高の友達であるアンドロイドを進化させていった。
今では、外見や日常会話だけでは
人間と区別がつかないほど精巧なフレンドロイドが
一般に普及していた。
そして、愛子のそばにも
物心がつくかつかない頃から1体のフレンドロイドが、
友達としてずっと近くにいた。
フレンドロイドの名前は、イブ。
愛子が成長していくうちに、
フレンドロイドのイブも性能を上げ、
“成長”を遂げていった。
愛子とイブは、一緒に思い切り野原をかけまわり、
お人形さんごっこをやり、
同じものを見て、同じものに触れ、
たくさんのおしゃべりをしてきた。
もちろん愛子には人間の友達もいたが、
それでも自分の事を一番理解してくれているのは
ずっとイブであることは変わらなかった。
イブは、他の友達が所有している
どのフレンドロイドよりも、優秀だった。
愛子の父がフレンドロイドの研究開発者であったため、
イブに最新の技術を常に注ぎ込んでくれていたからだった。
父はフレンドロイドの開発者として家族を支え、
母はイブを含めた家族を、優しい愛情で包んでいた。
愛子はそんな両親を尊敬していた。
愛子とイブは、生身の人間と機械という違いはあったものの、
二人とも両親が生み、育ててくれたという意味においては
互いが唯一無二の「姉妹」であるとも言える存在だった。
愛子は、両親とイブ、そしてたくさんの友達や
大人たちに囲まれて、すくすくと育っていった。
しかし。愛子が高校生になった時、
愛子を取り巻く環境に大きな変化があった。
——–父の失踪。
原因は、まるでわからなかった。
周囲の人は、
「愛人を作って逃げ出した」とも、
「研究開発費を使い込んだのだ」とも、
「ライバル会社に情報を流出させた」とも、
さまざまな噂をささやきあった。
しかし、真相はわからなかった。
母は、父の失踪について、何も教えてくれなかった。
ただ、淡々と日常生活を続ける努力をするだけだった。
少なくとも表面上は。
愛子は、父の事が許せなかった。
どんな理由があったにしろ、
私たち家族を放って逃げるなんて。
そんなのは、私たちに対する裏切りだわ。
せめて、どんなことがあったのかを
教えてくれてもよかったのに。。。
「愛子、お父さんを探そうよ」
イブは、愛子の目をまっすぐに見つめながら
なめらかな口調で言った。
イブはアンドロイドのため、愛子のような感情はない。
「優しさ」や「愛情」に似たものはプログラミングされていたが、
それは状況に対する反応プログラムであり、
実際のところは、良く分かっていなかった。
開発者の間では、人間の感情を持たせることが
「フレンドロイドプログラムの最後の壁」
とも言われていた。
しかし、そんなイブでも愛子が傷ついている事は理解できるし、
自分の生みの親である人物の失踪を、
「処理」できないでもいた。
「直接お父さんに会ったら、何かわかるかもしれないし」
イブの説得の声は、そのまま愛子の気持ちを表していた。
とにかく、会わなければ何も分からない。
そして、愛子とイブは、母親には何も告げずに
二人だけで父親探しを始めることにした。
父親の居所を探す作業は、困難を極めた。
父の同僚や、父と昔から仲の良い人に聞いても、
父の居所のヒントにはならなかった。
父を探す旅は、はじめは近隣からはじまったが、
しだいに探す範囲が広くなってゆき、
愛子とイブは全国各地を飛び回ることになっていった。
さらに、父が失踪してしまってからは
イブのメンテナンスをしてくれる人がいなくなってしまった。
もちろん専門の技術者に依頼すれば
メンテナンスはしてもらえる。
しかし、「姉妹」であるイブを、他人に見てもらうのは
愛子には抵抗があった。
幸い、父のメンテナンス風景をみていることもあり、
ある程度の知識があったので、
愛子は自分でイブのメンテナンスをすることにした。
自分の姉妹、自分の相棒と共に、
二人の父を探す旅。
愛子は学校を卒業し、技術者として働きながら、
休みの日にはイブと共に父の消息をたどる日々を
送っていった。
しかし、なかなか父の足取りは、つかめなかった。
急接近したように思うと、
父の姿は、またかき消えてしまった。
そんな日々を過ごして、3年が過ぎ去った。
「お父さんは、もうこの世界には
いないのかもしれない。。。」
そんな風にも思えたある日。
「愛子!あの人!」
イブがささやきながら、小さく指差した。
父だ。
だいぶ老けこんだ様子にはなっていたが、
間違いない。
今までどこにいたのかは分からないが、
父は現在、自分の住んでいる町にいたのだ。
愛子とイブは、父に気づかれないように
父のあとを追った。
父は二人に気づく事もなく、
ややうつむき加減に歩き続け、やがて
一軒の家に行きついた。
父は自分の名字(つまり愛子の名字でもある)
が書かれた表札が下げられている小さな家に、
「ただいま」
と言いながら戸を開けると、中から
「おかえりなさい」
と、女性が出迎えた。
その女性は、若くも美しくもない
白髪交じりの初老の女性だったが、
父とその女性の姿を見ると、
互いに信頼し合っている関係であることが見て取れた。
* * *
帰り道。
「なんでお父さんと直接話さなかったの?」
と、何度も聞くイブを無視しながら、
愛子は久しぶりに実家へと行くことにした。
母は、今はひとりで暮らしている。
愛子自身の仕事の関係もあったが、
父の事を何も話してくれなかった母と
ぎくしゃくした関係になっていたのも事実だった。
私は、今日の事を母に話して、
一体、どうしたいんだろう?
愛子はそんな風にも考えたが、
足は自分の意志とは無関係に、
自分が幼いころの時間を過ごした家へと向かっていた。
母は、突然の訪問にも関わらず、
二人を喜んで出迎えた。
愛子は、たわいもない話だけして帰ろうか?
とも考え直したのだが、母の方から
「何か話したいんでしょう?」
と水を向けられてしまった。
そこで愛子は、今日見たことを、
母にぽつりぽつりと話すことにした。
母は黙って聞いていた。
愛子が全てを話すと、母は
「教えてくれてありがとうね。
愛子も、イブも、よく頑張ったわね」
とねぎらってくれた。
その後、数瞬間をおいて、最後に母は
ためらいがちにひと言、つぶやくように二人に告げた。
「でもね。
最初にお父さんを裏切ったのは、お母さんの方なの。
お父さんは、それで出て行ったの」
ふと見ると、畳に母のものではない
短い髪が落ちていた。
* * *
「愛子、やっぱり分からない。
お父さんのことも、お母さんのことも。
そして、一番分からないのは、愛子のこと」
イブは二人で暮らしている部屋に戻ってくると、
自分が「処理」しきれないことを、愛子に問いただした。
「なんで、お父さんと直接話さなかったの?
そして、なんでお母さんを責めないの?
愛子が、一番傷ついているじゃない?」
愛子は黙っていた。
イブは黙っている愛子に向かって、問い続ける。
フレンドロイドであるイブは、
相手を傷つけない程度には、人間に反論ができる。
「私、ぜんぶ覚えているよ?
お父さんに会いたくて愛子が泣いた夜も。
どんなに探しても見つからなくても、
ずっと諦めずに歩き続けた日の事も。
お母さんに相談したくても、できなかった愛子も。
それよりずっとずっと前に、
愛子の家に私が来てからのこと、
ぜんぶ覚えてる。
だから・・・」
「ねぇ、イブ」
愛子は無理に笑いながら、イブに向き合った。
「いいのよ。イブ。
お母さんに何があったのか?
お父さんがその後どうして今の生活を選んだのか。
もう、いいの」
「よくないよ!
愛子は嘘をついているよ。
私のセンサーをごまかせると思っているの?」
イブには感情はない。
ただ、ずっと一緒にいた愛子の、
あまりにも不合理な態度に「正解」を求めようとした。
愛子は、ゆっくりと口を開いた。
「イブ、あのね。
人間って、弱いんだ。
ちょっとしたことで、すぐに逃げるし、
イブみたいに何でもずっと覚えていられないし、
何でも自分勝手にやったあと、嘘もつくし。
そして、自分は逃げて、覚えてなくて、嘘もつくクセに
自分以外の人はそうじゃない事を求めたりして。。。」
イブは、愛子の話を黙って聞いていた。
「近くにいる人の事を分かったようなつもりで、
いい気になって。
イブみたいに、感知センサーが
付いているわけでもないのにね。
でもね。。。」
愛子は、自分でも泣いているのか笑っているのか
分からない表情のまま、イブの肩を抱いた。
「自分が不完全って分かっているから、
だから、時には自分が傷ついても、
他の人を許せたりもするんじゃないかな?」
* * *
数年後。
フレンドロイドに革命的な事件が起こった。
今までの常識では考えられないプログラムが開発されたのだ。
そのプログラムで動くフレンドロイドは
「忘れてしまう」
「嘘をついてしまう」
「センサーがついていないため、
相手がどう思っているのかを、
何となくしかわからない」
そんな欠陥を持っていた。
しかしその結果、人間と同じような感情、そして愛情を
フレンドロイドが持てるようになった。
不完全だからこそ働くプログラム。
そのプログラムは、開発者の名前を冠して
「アイコ&イブ」
と名付けられていた。