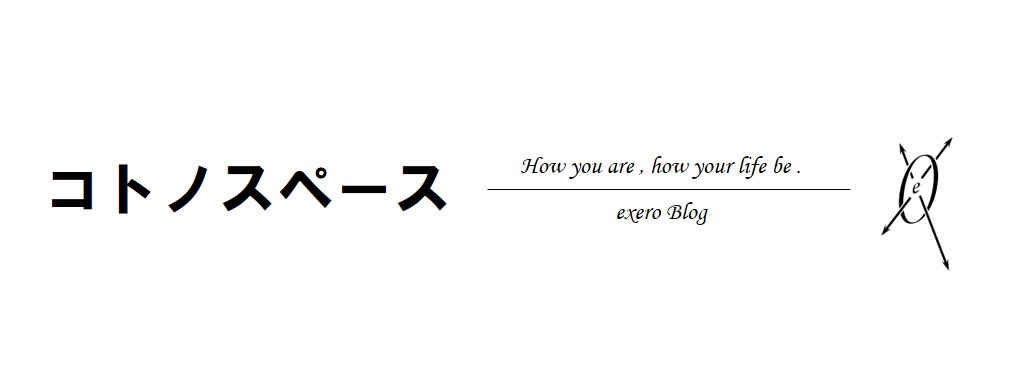あるところに、幼なじみの少年少女がいた。
二人とも早くに親を亡くしていたが、
優しい村の人たちに包まれて育ってきた。
二人はこの年になるまで村から出たことがなく、
素朴に、純粋に生きてきた。
しかし、成長するにつれて、
二人とも村の生活に退屈さを感じ始めるように
なってきていた。
毎日変わることのない生活。
自然には恵まれているけれど、
それ以外には何もない、この村。
「ここで、一生このまま過ごすのか。
なんか、つまらないな」
少年がそう言うと、少女も、
「ええ、私、もっと幸せになりたいわ。
大人たちが言っていたけれど、東の方には
ここよりもっと刺激的な都会があるらしいわ」
とうなずいた。
「私たち、ここで終わるような人じゃないと思うの。
ねぇ、私たち都会に出てみましょうよ」
「そうだな。
でも、一緒に行くのはつまらない。
お互いが充分幸せになってから再会するというのは、どうだ?」
「わかったわ。
私、都会で、あなたがびっくりするほど幸せになるわ」
「よし!じゃあこうしよう。
1つ季節がめぐった日の今日、この桜の木の下で再会しよう。
その時、お互いの幸せを確認し合おうじゃないか」
少年と少女はこう話し合うと、
小さな丘の上で力強くそびえたち、
満開の花を咲かせている桜の下で誓い合った。
この桜は、古くから「神木」として崇められていて、
この桜を拝みに来るために、わざわざ遠くの村から
やってくる人もいるほどの木だった。
「きっと、この桜も
僕たちの幸せを応援してくれるに違いない」
少年と少女は、桜の木を見上げながら
自分たちの未来に心を躍らせた。
少年はふと思い立ち、
「この木は、ご神木らしいから、
きっと僕たちを守ってくれるに違いない。
この桜のまわりにある土を、お守り代わりに
ちょっと持っていこう」
少女もそのアイディアを気にいり
「それは素敵ね!
どうか私たちに、幸せが訪れますように」
と言いながら、桜のそばの土を少しだけもらうことにした。
そして、二人はもう一度再会を誓いあうと、
別々に都会への道を歩いて行った。
—
少年は、都会へと出てきた。
今まで見たことの無いような、刺激的な街並み。
行きかう人も、今まで見てきた村の人たちとは
まるで違っていて、洗練されていた。
少年は、目にとまった店に入ってみた。
そこには少年が今まで見たことの無いような
美味しそうな食べ物が、ところ狭しと並んでいた。
少年が一番近くにあった食べ物を手に取り、
口に入れようとしたその時、
「おい、小僧。ちゃんと金を払え」
と、見知らぬ男に手を掴まれた。
「え?金って?」
少年はびっくりして答えると、男は
「なんだお前?金を知らないのか?
小汚い小僧だと思っていたが、そこまで田舎者とはな!」
と言いながら、少年を蹴り飛ばした。
「金がないなら、何も手に入らない。
それが街のルールだ。
わかったら、さっさと田舎に帰りな!」
男は吐き捨てるように言うと、
少年を店からただき出した。
少年は、あらためて街の人々を見てみた。
街の人々は、何かを受け取る時、何かをやってもらう時、
必ずポケットから何かを出して、相手に渡していた。
そして、その紙きれ、あるいは丸い金属片を受け取ると
都会人たちは決まって笑顔になった。
きっと、あれが“金”というものなのだろう。
そして、この都会では“金”がある人が
笑顔を向けてもらえるらしい。
今までいた村とは全く違うルールだった。
村では、必要なものがあればみんなで作り、
みんなで分けて過ごした。
何かを作るのが得意な人がいたら、
その人が作り、必要な人がそれをもらっていった。
しかし、都会では違うルールがあるらしい。
「僕は、都会で幸せをつかむと決めたんだ。
だから、都会のルールを覚える。
でも、お金って、
どうやって手に入れられるんだろう・・・?」
—
少女も、都会にやってきた。
見たこともない服装、見たこともないきらびやかな人々。
まさに圧倒されるとは、このことだった。
街では、男の人が道行く女性たちに声をかけていた。
「ねぇ、一緒にお茶でも飲まない?」
しかし、男の人が声をかけても
女性たちは歩みを止めることもなく無視をし続けていた。
少女はその男の人がかわいそうになり、
男の人に声をかけた。
「あの、一緒にお茶を飲む人を探しているんですか?
なんなら、私が一緒にお茶を飲みましょうか?」
男はふり返り、少女を値踏みするような目で見ると
急に怒りだした。
「ふざけんなよ!
なんで俺が、お前みたいに芋くさい奴と
お茶を飲まなきゃいけないんだよ!?
俺がお茶を飲みたいのは、
美しい女性だけなんだよ!」
男は「しっしっ」と野良猫を追い払うようなしぐさをした後、
また道を歩いている女性たちを追いかけ始めた。
少女は親切心のつもりで男に声をかけた。
村では、困っている人がいたら、助け合うのが
当たり前だった。
でも、都会ではルールが違うらしい。
少女は、あらためて街の女性たちを見た。
女性たちは、競うように颯爽と歩き、
自分たちの外見をアピールしていた。
男性同士、また女性同士の会話も聞こえてきたが、
どうやら都会の女性の価値は「美」によって
決まるらしい。
村では、そんなことはなかった。
みんなが一緒に働いて、
それぞれがそれぞれの役割を果たしていただけだった。
都会には、都会の価値観があり、
「優劣」というものがあることを知った。
「私は、都会で幸せをつかむと決めて村から出てきた。
だから、都会のルールを覚える。
でも、美って、なんなの?
どうやったら手に入るの・・・?」
—
桜は満開の時期を終え、
活き活きとした葉をつけ始めていた。
—
少年は途方に暮れ、とぼとぼと道を歩いていた。
道に迷い、いつの間にか裏路地の方へと来てしまった。
すると、あきらかに人相の悪い数人のチンピラが
少年を取り囲んだ。
「おい、小僧。
誰がここを通っていいって言った?」
チンピラの1人が少年を小突いた。
「ごめんなさい・・・」
少年は反射的に謝ったが、
チンピラ達は少年の弱気な態度を見ると
ますます調子に乗って脅してきた。
少年の腹を一発殴ると、
チンピラは勝手に少年の持ち物をあさりはじめた。
「なんだこいつ。
ほとんど何も持ってないじゃないか」
「袋に何か入っていると思ったら、
土だぜ、土!」
「役に立たねぇ奴だな」
チンピラが口々に話をしているところに。
「おい、お前ら何やってんだ?」
チンピラはその声の主に目をやると
「あ!兄貴!お疲れ様です」
と、急に静かになった。
兄貴と呼ばれた男は、倒れたいた少年に近付くと、
「大丈夫か?」
と声をかけた。
「こいつ、この街にいるのに、
一銭も持ってないんですぜ?
持っていたのは、こんな土くれだけで・・・」
チンピラは兄貴と呼ばれた男に
少年が桜の木の下から持ってきた土を指しだした。
兄貴と呼ばれた男は、渡された土を
しばらくずっと見ていた。
その目は、はじめは驚きの色を示し、
その後に、したたかな光を宿した。
兄貴と呼ばれた男は、少年を抱きかかえると
少年に問いかけた。
「こんなにボロボロになってかわいそうに。
俺のアジトで、ゆっくり休むといい。
ところで、この土は、どこで手に入れたんだい・・・?」
—
少女は、ひどく疲れていた。
都会の人は、少女を冷たくあしらった。
都会の男も、女も、少女を値踏みするように一瞥すると
「あっちへ行け!」
と、追い払った。
たまに優しくしてくれる人が現れたが、
ろくな連中ではなかった。
「どうやら、美しくないと価値がない、というのは
この街の絶対的ルールなのね」
と、少女は痛感した。
疲労困憊の中、フラフラと街をさまよっていると、
少女の目にひとつの看板が飛び込んできた。
「美の魔法の店」
少女は、不思議な雰囲気を持つその店に、
いてもたってもいられずに飛び込んだ。
「いらっしゃい」
そこには、年齢がまるでわからないが
とても美しい女性が座っていた。
都会人の言う美があまりよく分からない少女にも
その人は、とても美しく見えた。
少女は、思い切って女性にたずねた。
「あの・・・どうやったら、
みんなに愛されるような美しさを
手に入れられるんですか?」
魔法の店の女主人は少女を見ると、
ガラスのように透明な声で少女に言った。
「あらあら。
あなたは充分きれいよ。
ただ、この街にいる人には
わかりにくい美しさなのね。
あなたが対価を払うのならば、
私があなたを、どこまでもきれいにしてあげる。
でも、私の魔法に見合うだけのものを
あなたは持っているかしら?」
少女は、
「わたし・・・何も持っていなくて・・・」
と言いながら、自分の持っているものを
目の前にあった机に並べ始めた。
女主人は、次々と机に出される「ガラクタ」に
興味を示さなかった。
しかし、一番最後に机に出された
小さな袋だけは、違った。
女主人は小袋を開けて、中身を確認した。
中には、少女が桜の木の下から持ってきた
土が入っていた。
土は、魔法の店のうす暗闇では
小さくキラキラと輝いていた。
女主人は、少女にこう答えた。
「ホントはこんな土欲しくないけれど、
あなたがどうしてもと言うのなら、
これと交換に、あなたを美しくしてあげるわ」
—
桜の木は葉を落とし、
季節は秋を迎え始めていた。
—
少年は、ギャング団の一員になった。
とは言っても、少年のやることは簡単だった。
たまに自分の田舎に帰り、
桜の木の下から土を取ってきて、
“兄貴”に渡すだけ。
たったそれだけのことで、
兄貴は少年にお金をくれた。
兄貴が「土」を、何に使っているのかは
詳しくは知らなかった。
ただ、
「お金持ちで欲しがる人がいる」
とだけしか聞くことはなかった。
少年は、自分を助けてくれた兄貴のために、
せっせとご神木の「土」を持ってくる。
たまに昔の村人に見つかり、
「なんてことをしているんだ!」
と追いかけられることもあったが、
そんな時は逃げた。
何回も繰り返しているうちに、
村人は少年を警戒するようになっていった。
しかし、しだいに少年も体が大きくなってゆき、
時と共に村人に対する申し訳なさも、
やさしさもなくなっていった。
追いかけて来る村人に
暴力をふるうようなことも増えて行った。
少年は青年となり、
都会に染まれば染まるほど、
大きなお金を手にし始めた。
青年がお金を手に入れれば入れるほど、
青年にかしずく人が増え、尊敬を集めて行った。
青年は、都会のルールである
「お金=力」
という、「力のヒエラルキー」を
駆け上がって行った。
—
少女は、魔法のお店に
足しげく通うようになっていった。
魔法のお店は、少女の望みを
それこそ魔法のように叶えていった。
「みんなが私を大切にするような、
すてきな洋服が欲しいわ」
と言えば、女主人はそれを用意した。
「もっときれいなお化粧をしてみたい」
と言えば、きれいなお化粧もしてくれた。
そればかりではない。
「もっと、私の目を大きくしたいわ」
と言えば、女主人は不思議な魔法で
少女の目を大きくした。
「もっと美しい声になりたい」
と願えば、女主人は少女に
新しい、美しい声を提供した。
しかし、少女が何かを願うたびに
女主人は、ご神木の「土」を要求した。
少女は、なんで女主人が「土」を欲しがるか
まるで分からなかった。
女主人は、ただ
「この土には、魔法のエッセンスがあるのよ」
とだけ教えてくれた。
少女は、どんどん都会的な美しさを
身につけて行った。
少女が美しくなればなるほど、
街にいる男も女も、少女にやさしくしてくれた。
少女は美しい女性となり、街を歩けば
誰もがふり返るほどになっていった。
もちろん、それを維持するためには
ご神木の「土」が必須だった。
女性は自分の言う通りになる男たちに
「土」を取ってこさせた。
帰ってきた男たちは、たまに傷ついて帰ってきた。
村人との間に、どんなやりとりがあったのかはわからない。
しかし、そんなことは、どうでもよかった。
少女であった女は、
この街のルールである
「美のヒエラルキー」
を、ひたすらに駆け上がって行った。
—
桜は土を失い、むき出しになりかけた根をさらけだし
長い冬を迎えた。
—
春。
ひとつ、季節がめぐった。
めぐった季節はたったひとつだったが、
都会に出た少年と少女にとっては、
もう何年も経ったような、そんな気がしていた。
村と都会とでは、もしかしたら
時間の流れが違うのかもしれない。
そんな風にも思えるほどだった。
かつて少年だった青年は、
大きな富と権力を手に入れ、田舎へと帰ってきた。
かつて少女だった女性は、
都会的な美貌と声を手に入れ、田舎へと帰ってきた。
お互いが、どれだけ幸せになったのか?
それを確かめ合う約束を果たすために。
二人は、約束の桜の木がある丘を
別方向から登っていった。
以前は、美しくなだらかな丘であったが、
彼らが土を掘り返してしまったせいで、
その景観は失われていた。
男は、丘を登り切り、桜の前に立った。
女も、丘を登り切り、桜の前に立った。
二人は、再会した。
しかし、二人が再会を喜び合うことはなかった。
「桜が・・・咲いていない・・・」
いつも、この季節になると
桜は力強く、満開の桜の花を咲かせていた。
しかし、今、桜の木には、
ひとひらの桜のはなびらも咲いてはいなかった。
二人は、長い間沈黙した。
長い長い沈黙の後、男がゆっくりと口を開いた。
「君は、幸せになったかい?」
女は、はじめは気丈に「ええ」と答えたが、
しばらくするとうつむいて「いいえ」と
答えなおした。
男は、その弱気な態度と女の服装が
あまりにもミスマッチだったのに軽く笑い、
その後、女と同じようにうなだれて言った。
「俺も、幸せじゃない。
いつのまに、こんな風になったんだろう」
男は、力のヒエラルキーを駆け上がったはずだった。
女は、美のヒエラルキーを駆け上がったはずだった。
でも、その頂上には、幸せはなかった。
こんな小さな丘の頂上で見ていた景色の方が
まだ幸せに近かった。
二人は、今になって失ったことの大きさを
かみしめた。
自分の欲望のために、
大切な桜を傷つけてしまった。
大切な村の人たちを傷つけてしまった。
彼らが桜の木の下から奪っていたのは、
土だけではなかった。
彼らが自分が幸せになると思って、
せっせと都会に持って行った土の中に、
幸せはキラキラと輝いていたのだ。
—
男と女は、都会を離れ、桜の世話をすることにした。
もう一度、桜に咲いてほしい。
二人の願いは、共通していた。
都会は、男と女に厳しい洗礼を浴びせた。
男がギャング団をやめることを兄貴に伝えると、
兄貴は表情一つ変えずに
男からすべての財産と権力を奪った。
兄貴の価値観では、男は
「ただのつまらん男になりさがった」
無価値な存在だった。
女は、男ほど激しいことは起こらなかったものの、
時間が経つにつれて、女にかかっていた
「美の魔法」
は、衰えを見せ始めた。
声は元に戻り、
白く美しかった肌に、きめ細やかさは失われ、
大きかった目は小さくなっていった。
都会の人々は、男と女に
あからさまな軽蔑の目を向けた。
しかし、都会を離れる二人は、
それに耐えることが出来た。
しかし、困難は村に帰ってからの方が大きかった。
昔は、優しい信頼感で結ばれていた村人たちも、
男と女に辛く当った。
今まで自分たちがやってきたことを考えれば、
村人たちの態度は当たり前で、
村人たちを責めることは出来ない。
ただ、頭では分かっていても、そのつらい仕打ちは、
男と女の心を深く傷つけた。
それでも、二人は桜の世話をやめなかった。
最初は、桜に対する罪滅ぼしのつもりだった。
しかし、
ひとつ季節がめぐり、
ふたつ季節がめぐり、
いつつ、
そして十と季節が重なっていくうちに、
単なる罪滅ぼしの気持ちではなくなっていった。
誰かに教えられた幸せではなく、
自分たちで決めたこと。
それをただただつとめることに、
不思議な喜びを感じていた。
そして。
あれから、六十の季節がめぐった。
二人は、すっかり年老いていた。
村人の中には、いまだに陰口を言う人もいる。
しかし、大部分の村人は、男と女を許していた。
過去の二人を知らない子供や若者も増えている。
六十の季節がめぐっても、
あれ以降、桜は一度も咲いていない。
でも、二人は不思議と穏やかな気持ちだった。
男は、妻となっていた女に言う。
「君は、幸せになったかい?」
女は、夫となっていた男に、自然に答える。
「ええ」
男は目を細めて笑うと。
「俺も幸せだ」
と答え、もう一度かみしめるように
「幸せだな」
と言った。
春の足音が、もうそこまで聞こえてきていた。
丘の上の桜には、
春を待ち望んでいるかのように、
たくさんの大きなつぼみが膨らんでいた。