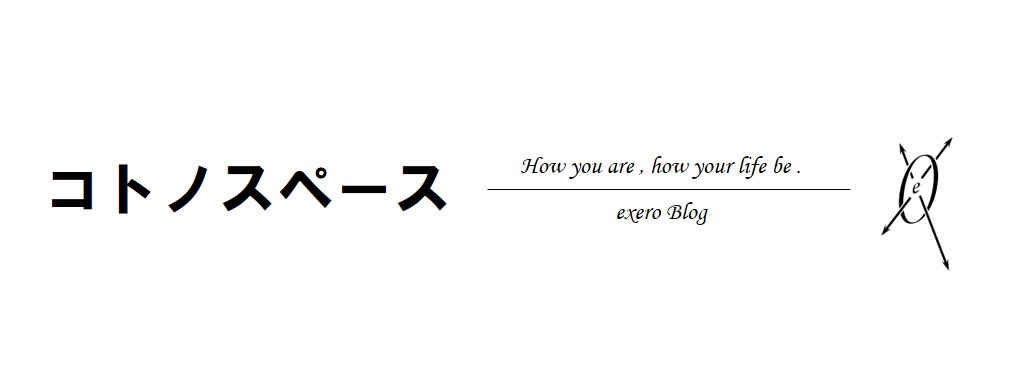僕は今日も、いつものように目覚めた。
窓に目をやると外は大嵐のようだったが、
完璧に温度管理された室内では、
その景色は単なる映像のように見えた。
いや、僕が見ているこの嵐は、
実際のところ、本当に映像なのかもしれない。
なにせ僕は、この施設から外に出たことがないのだから。
暑い、寒いも感じたことはないし、
空腹も感じたことはない。
それらのすべてを
単に知識として学んだことはあるけれど、
「暑い」も、「寒い」も、「空腹」も、
そして、「絶望」も、「至福」も、
実際に体感をしたことはない。
ここは、すべてがコンピュータとロボットで
管理された、電子の城。
何も不自由がない代わりに、
自由そのものも、存在が許されていない空間だった。
—-
僕はどうやら、かつて「ニンゲン」と
呼ばれていた生物らしいが、
はっきりとは分からない。
僕は自分と同じ仲間に出会ったこともない。
僕の友達は、僕とは似ても似つかない姿の
ロボットだけだった。
友達のロボットは、僕に教えてくれる。
はるか昔は、僕のような「ニンゲン」が
たくさんいて、支配者のようにふるまっていたらしい。
しかし、愚かな行為を繰り返すうちに
だんだんと数が減り、今では僕以外には
ほんの数体しか残っていないらしい。
どれくらいの数が残っているのか?
それは僕には、たしかめようもないし、
たしかめられたとしても、さほど重要には思えなかった。
「きみは、保存すべき貴重なサンプルなんだ」
そんな風に言われたけれど、
僕からしてみればピンとこない。
生まれた時からこの建物にいて、
施設内にあるどんな食べ物も食べていいし、
なにをして遊んでもいい。
窓からは外の世界が見えていたものの、
それに何かの意味や価値も感じることはないのだから。
「時期が来れば、きみと同種のメスに
会わせてあげよう。
サンプルとして、この扉の向こうで生きている」
とロボットに言われていたけれど、
それにも特別な感情はなかった。
いつもの日常。
いつもの平和。
白い壁に覆われたこの施設が
僕の世界のすべてであったし、
それになんの文句も、疑問もなかった。
そこに。
窓の外が一瞬まぶしく光ったかと思うと、
数瞬置いて、今まで聞いたこともないような
轟音が響き渡った。
窓から外を見てみると、
大空に暗雲が立ち込め、雷鳴を怒らせていた。
大蛇の舌のように大地を舐めながら、
何本もの稲光が、白亜の塔を襲っていた。
施設内にアラームがけたたましく鳴り、
今日という日が、非日常に染まったことを
知らせていた。
初めての体験に恐ろしさを感じながらも、
どこか気分が高揚している。
僕にとっては、
この「恐ろしさ」もはじめてだし、
なにより「気分の高揚」なんて、初めて味わう感覚だ。
僕は施設内を走りだした。
自分でもよく分からないこの気持ちに
「走る」という行為が似合っている気がしたからだ。
—-
「あれは、、、?」
施設内を走っているうちに、
今まで閉ざされ続けていた大扉が
開かれているのに気がついた。
その扉は、「時期」が来た時に
僕の同胞に会うために開かれるはずの扉だった。
今がその時期なのか?
いや、おそらく何らかのトラブルなのだろう。
僕が、開け放たれた扉の前で呆然としていると、
「あ、、、あの、、、」
と、扉の向こうから、おずおずと声をかけてくる
存在があった。
それは僕と同じ姿をした生物だった。
少しだけ僕と違うような気もしたけれど、
間違いなく、今まで会ってきたロボットたちとは違う。
僕たちは、どちらからともなく
「同種」のにおいを感じ取り、
近づき、互いの手と手を合わせた。
「こっちにきて!」
僕と同種の「それ」は、僕の手を引きながら走り始めた。
相変わらず警報は鳴り響き、
非常事態を告げるメッセージが
空間に現れては消えてゆく。
「もう一か所、開かなかった扉があるの。
そこを、一緒に見に行きたい!」
「わかった。一緒に行こう」
ロボットとしか意思を疎通しなかった声が
今、アラームにかき消されそうになりながらも
のどを響かせている。
こんな単純なことなのに、気持ちがいつもと違う。
これが「喜び」「興奮」というものなのか?
僕は手を引かれながら、目的の扉まで息を切らせた。
—-
「ここ。。。やっぱり開いてる」
つないでいた手をほどき、
僕たちは大きく口を開けた扉の奥へと進んで行った。
奥には、らせん状に続く道が続いていた。
僕たちを認識すると、
道は自動的に動き出し、僕たちを
らせんの下へと送り始めた。
今までの警報の喧騒とは
うって変わって、道が動く静かなモーター音だけが
そこには、こだましていた。
エスカレーターの一段一段がうろこのように
うねる様は、さながら
とぐろを巻く蛇を連想させた。
もちろん、それも単なる知識でしかないのだけれど。
歩道は、最下層まで僕らを送り届けると、
自然と動きを止めた。
「あれ。。。。なんだろう?」
そこには、今まで見たことのないようなものが
おごそかに安置されていた。
銀色に光るそれは、
二枚の板が折り重なるような姿をしていて、
一方はツルツルに磨き上げられた板が、
そしてもう一方には、おびただしい量のボタンが並んでいた。
「なんなの、、、これは?」
僕の手を引っ張ってきた同胞は、
中でも目立つボタンのひとつを押した。
すると。
磨き上げられた板に映像が表出し始めた。
これは、画面だったのか!?
あまりに原始的なものだったので気が付かなかったが、
磨き上げられた板は画面で、
整然と並んだボタンは、なにかを入力するためのもののようだった。
画面に映し出された映像は陳腐で、
粗末なものであったが、そのどれもが
初めて目にするものばかりだった。
そこには、たくさんの僕たちの同胞が
笑い、
泣き、
唇を重ね、
創造し、
破壊し、
命を奪い、
命を育み、
生きて、
死んでゆく、
そんな姿が、絶え間なく流れては消えていった。
—–
僕たちは、その映像を
どれくらい見ていたのだろう?
ほんの数時間だったのかもしれないし、
何日も、何カ月も見ていたのかもしれない。
僕たちは、その映像に見入り、
たまに互いの顔を見合わせながら、
同じ時を刻んでいた。
すると、「彼女」はポツリと言った。
「やだ、、、、私たち、裸じゃない。
。。。恥ずかしい。。。」
「彼女」に言われて、初めて気が付いた。
そうだ。僕たちは裸だった。
完璧な温度管理がなされた
この施設内で、裸でいるのは、ごく当たり前だった。
いや、なんで、今まで「当たり前」だと思っていたのだろう?
彼女の前で裸でいるなんて、恥ずかしいじゃないか。
僕たちが互いに恥ずかしがっていると、
突然、スピーカーからロボットの音声が流れてきた。
「あなた方は、旧世界の知識を得てしまいました。
すでに、純粋なサンプルとしての価値はなくなりました。
残念ですが、ここから追放処分とします」
その声が終わるか終わらないかのうちに、
僕たちの立っていた床がパカリと割れ、
僕たちは施設の外へと放り出された。
—-
僕と彼女は、はじめて外の空気を吸った。
なにやら濁ったような、砂まじりの空気。
でも、僕は、彼女とならば
生きていけるような気がしていた。
僕の目を見つめる彼女からも、
そんな意思を感じ取れた。
僕たちは、きっと、この何もない外の世界で
肩寄せ合って生きていく。
僕たちは大地に落ちていた葉を拾い、
身体にまとった。
嵐の去った外の世界は、さほど寒くはなかったけれど、
とにかく、彼女の前で裸でいることが
恥ずかしかったから。
僕たちは、歩き始めた。
不安げな表情をしている彼女。
僕は、彼女の目を見て、こうつぶやいた。
「愛してるよ」
彼女は、ゆっくりと微笑んだあと、
僕の言葉に応えるようにうなづいた。
そして僕たちは、やさしい口づけを交わした。
—
彼らに「世界」を見せた白銀の機械は、
彼らの背中を見送るように
大地に打ち捨てられていた。
その白銀の機械には、
かじられた りんごのマークが刻印されていた。
True Title ~ 『 Adam and Eve 』