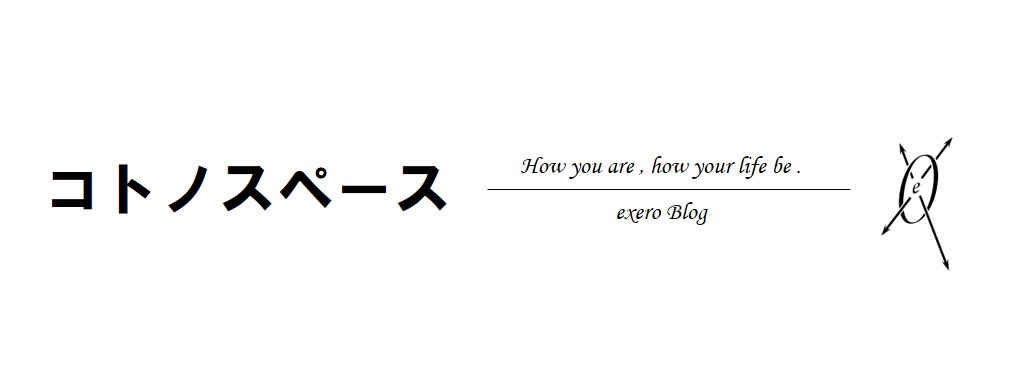彼女の父は、いつも仕事ばかりしていた。
彼女が小さい時も、彼女が学生の時も
彼女の目に焼き付いているのは
研究室で考え事をしている父の後ろ姿だけだった。
たしかに、父の研究の成果は素晴らしかった。
それは、彼女自身、誰よりも理解していた。
彼女の父は、コンタクトレンズにコンピュータを内蔵させ、
いつでもどこでも世界中の情報にアクセスできるようにし、
それを「スマート・アイ」と名付けた。
人々は、スマート・アイを通して
自分の目の前に映し出される映像から、
様々な情報を入手することが出来る。
そして、何もない空間を手で操作するだけで、
レンズが手の動きを読み取り、また新たな情報にアクセスできる。
ほんの十数年前までは、
多くの人々がポケットに携帯端末をしのばせていたのが
はるか昔のできごとのようだった。
今や、彼女の父の作ったスマート・アイがなければ、
世界の人々は、日々の生活にすら支障をきたしてしまうほどの
普及ぶりだった。
でも、彼女が欲しかったのは、父の偉大な業績ではなく、
父と一緒の時間だった。
彼女が父と遊びたい時も、父は仕事をし続けていた。
彼女が入学した時も、卒業式を迎えた時も、
父は研究室に閉じこもり、彼女は自分の晴れ姿を見せられなかった。
彼女が悩み、父に相談をしたい時も、
父は彼女に向き合ってくれることはなかった。
それどころか、
最近、彼女のフィアンセがあいさつに来た時ですら、
ひと言「どうも」と言ったきり、研究室に閉じこもってしまった。
彼女は、そんな父への不満がたまりにたまり、
とうとう心からの怒りをぶつけた。
「お父さんは、私のことが嫌いなの?
いつも仕事ばかりで、一度だって
私のために時間を使ってくれないじゃない!?」
研究者である父は、娘がなぜ怒っているのかも理解していない様子で、
「私がお前のことを嫌っているだって?
そんなことはないぞ」
と言いながらも、目は研究データをまとめた書類から
離れることはなかった。
彼女は、そんな父の態度に
「せめて、一日だけでも、私のことを見てよ!」
と言葉を荒げると、父は、
「わかった。
じゃあ、半年後のお前の結婚式の日は、
どんな事があっても、お前を心から祝福しようじゃないか」
と伝えると、すぐに仕事に没頭し始めてしまった。
彼女はまだ言い足りないこともあったものの、
父が約束してくれたことに満足をして、
自分の結婚式の準備を進めることにした。
しかし。
父と交わした約束は、結局果たされることはなかった。
父と約束をしてからしばらくすると、
父の身体に病巣が発見された。
そして、悪性の病魔は、数か月のうちに
いともたやすく父の命を奪い去っていってしまった。
「結婚式の日は、ずっと娘を見る」という約束は、
天国へと旅立った父と一緒に、彼女の手から
こぼれ落ちてしまった。
「お父さん。最後まで私を見てくれなかったね」
彼女は純白のウェディングドレスに身を包みながら、
結婚式の待合室でひとりつぶやいていた。
「まもなく、お時間です」
案内役の声で我に返った彼女は、
気を取り直して椅子から立ち上がった。
教会。
真っ白なバージンロード。
扉の先に待つフィアンセ。
どれもが彼女が夢見ていた光景だった。
ただひとつ、隣にエスコートしてくれる
父がいないことを除いては。
彼女の母が、彼女の隣へとやってきた。
彼女の母は、そっと彼女の手を取ると、
「これ。お父さんから」
と、金属性のチップを手渡した。
「え?なに?」
と彼女は不思議そうに受け取る。
その金属チップは、父の開発したスマート・アイに
新しいプログラムを追加するためのもので、
今では珍しくもないものだ。
彼女は、
「なんで、こんな大事な時に。。。」
と、訝しく思ったが、母の優しくも真剣なまなざしを見て、
自分のスマート・アイに、新しいプログラムを追加した。
すると。
「おまたせ。じゃ、じゃあ、行こうか」
目の前に、父が現れた。
いや、正確には、スマート・アイが見せている
父の映像なのだろう。
しかし、その映像は、体温までも感じられそうなほど
その場に父がいるとしか思えないほどのものだった。
母は微笑みながら彼女に伝えた。
「お父さん、病気が見つかった後は、
このプログラムだけ作っていたの。
“最後くらい、約束は守らないとな”って言いながら」
教会の扉が開いた。
彼女は、父にエスコートされながら
純白のバージンロードを、ゆっくりと歩いてゆく。
新郎にも、
神父にも、
式に参列しているすべての人にも、
新婦と父の歩みが見えている。
すでに全員に手渡されていた新しいプログラムは
その場にいるすべての人に、父の姿を見せていた。
祝福を受けながら、彼女は隣にいる父の顔を見た。
父が見慣れた、仏頂面の父だった。
「映像なら、もっとカッコよく修正してもいいのに」
と彼女は心の中で思ったが、
なにも手を加えないのが父らしくて、
ベールに隠れて「ふふっ」と微笑した。
結婚式、そして披露宴。
父は、約束通り彼女を一日中見守り続けた。
披露宴に参加しているすべての人も、
彼女の父がその場にいるものとして、
ずっと温かく見守ってくれている。
それだけ父の技術も素晴らしかったのだろうが、
彼女は、参列者の人たちの心遣いにも感謝した。
披露宴の会場を一度退席し、お色直しをしている最中、
彼女は、自分のスマート・アイに
一通の電子メールが来ている事に気がついた。
差出人は母で、件名には
「お父さんにはナイショね」
と書いてあった。
彼女はスマート・アイごしに電子メールを開いてみると、
目の前には、昔の、古い古い映像が浮かび上がった。
数々の、彼女が初めて目にする映像たち。
赤ん坊の彼女を目の前にして
「これは、どうやって抱くんだ?」
と、オロオロしている、若い頃の父。
彼女の入学式、そして卒業式のたびに、門の外で
「母さん!絶対に、来たことを話すなよ」
と、カメラの前で、あわてふためく父。
彼女が当時悩んでいたことに関する本を
一生懸命に読みながら、
「なぁ母さん。
こんなアドバイスをしてやってはどうだろう?」
と提案をしている父。
そして、フィアンセがあいさつに来る前、
何回も何回も
「娘をよろしくお願いします」
と、彼女のフィアンセへの言葉を練習をしている父。
すべてが、彼女の前では決して見せなかった
父の姿だった。
でも、すべてが本当の父の姿だった。
父は、いつでも彼女を見ていたのだ。
ただ、その事実を見せていないだけだったのだ。
彼女は、胸に込み上げてくる気持ちを抑えきれず、
衣装室のかたすみで、
声をあげながら大粒の涙をこぼした。
お色直しが終わり、
温かい空気に包まれながら披露宴は進み、
お開きを迎える時間となった。
新郎新婦は、ひな段から降り、
家族が並ぶ下座へと誘導された。
そこには、当たり前のように
父の姿も見える。
彼女は、案内係から封筒を手渡された。
その封筒の中には、
彼女が事前に書いておいた「父への手紙」が
おさめられている。
手紙には、天国にいる父への感謝の気持ちも伝えながらも、
どこか白々しく、逝ってしまった父への
やり切れない思いも綴られていた。
彼女は、自分自身が書いた手紙に
少し目を走らせると、目を伏せ、軽く首をふった。
そして、目の前にいる父を、まっすぐに見つめてから、
手紙には書いていない言葉を伝えた。
その言葉は、とても短いものであったが、
彼女の今の気持ちを、素直に表したものだった。
「お父さんへ。
世界一、スマートじゃない目で、
ずっと私を見守ってくれて、ありがとう。
世界一、鈍くて素直じゃない娘より」
彼女の目には、目の前にいる仏頂面の父が
心なしか笑ったように映った。