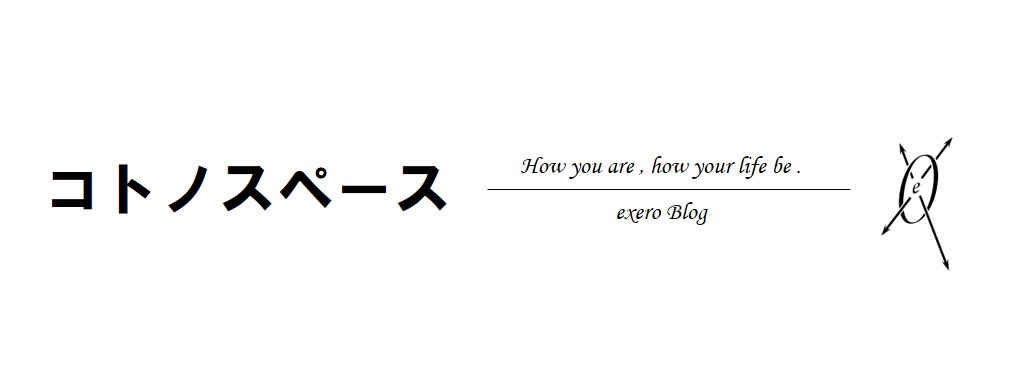いつの頃からだろう。
サンタクロースを信じなくなったのは。
子どもの頃のわたしは
けっこう無邪気で
小学校の高学年くらいまで真剣に
「サンタクロースは、いる!」
と信じて疑っていなかった。
でも、そんなわたしをみて友達は、
「えー、まだそんなの信じてるの?」
「サンタなんて、いるわけないじゃない」
と揶揄した。
その時わたしは友達から発せられた言葉に
内心ショックを受けつつも
「やだ、、、本気で信じているわけじゃないよ」
と、照れ隠し気味に笑ったんだったっけ。
「本当にいるんだよ!」
と、あの時
友達に言い返せなかったのは、
はやく大人になりたかった背伸びだったんだと思う。
そうか。あの頃から、わたしのサンタは
いなくなったのかもしれない。
—
街にはクリスマスソングが流れ、
きれいなイルミネーションで彩られている。
子どもの頃よりもきっと
もっと美しくなっている景色のはず。
でも、あの頃のようなワクワク感は感じない。
それは、わたしが大人になった、
ということなのかな。。。
頬を切るような冷たい風の中、
そんなことをぼんやりと考えていると、
「きゃっ!」
と、誰かがぶつかってきた。
「ごめんなさい」
どちらからともなく謝ると、
ぶつかってきた相手は、まだ小さな女の子だった。
最近の子にしては珍しく、
ちょっと やぼったい服を着ているけれど、
あどけなさがとても可愛らしい少女だった。
「大丈夫?」
「うん!これから帰るところ!」
と元気に答えるその子は、
うれしくてたまらないという笑顔を向けた。
「楽しそうだね。そっか、クリスマスだものね」
とわたしが言うと、女の子は
「うん!楽しさで はちきれそう!」
と両手をいっぱいに広げて
その場で軽く踊りはじめた。
こんな時期、わたしにもあったのかな?
と思いながら女の子を見送ろうとすると、
「ねね。お姉ちゃんは、サンタさんに
何をおねだりしたの?」
と聞いてきた。
「うーん、お姉ちゃんは
何もお願いしていないなぁ」
と答えると、その子は
「それじゃあ、サンタさん困っちゃうよ!
今からでもいいから、お願いした方がいいよ!」
と言って、一枚の折り紙をくれた。
「そこに欲しいものを書くんだよ」
と、女の子はピョンピョン跳ねながら言った。
そんな彼女のテンションに
少し圧倒されてしまったわたしは、つい、
「ありがと。でもお姉ちゃんのところには
サンタさんは来ないと思うなぁ」
と言ってしまった。
女の子は飛び跳ねるのをやめ、
わたしを見上げながら、こう聞いた。
「なんで?」
しまった。
せっかく楽しんでいる子に
変なことを言ってしまった。
わたしは彼女に気遣うように
「えーと。。。ほら、サンタさんは
子供にプレゼントを配るので忙しいから、
お姉ちゃんは遠慮しておくんだよ」
と言うと、女の子は不満そうに、
「えー、そんなのサンタさんも
つまらないよ」
と頬をふくらませた。
女の子は続ける。
「お姉ちゃんだって、
誰かを喜ばせようと思ってる時に
遠慮されたら、がっかりするでしょう?
サンタさんだって、うれしい!って思ってくれる人に
プレゼントを渡したいんだよ」
「そうかもね。。。でも。。。」
わたしが気乗りしない返事を返すと、
女の子は、
「もしかしてお姉ちゃん
サンタさんなんていない、と思ってない?」
と聞いてきた。
突然の質問に、わたしが面食らっていると
女の子は
「お姉ちゃん。
お姉ちゃんは、もしお姉ちゃんのことを
”そんな人はいない”って言う人がいたら、
仲良くしたいと思う?」
と言った後、にこりと微笑んだ。
「そんな風に言われたら、
せっかくプレゼントを用意していても、
寂しくなって、来なくなっちゃうよ。
サンタさんだって、同じ気持ちだと思うんだ。
だから、サンタさんにやさしくしてあげて。
1年に一回、会うのを楽しみにしてるんだから」
そう言って女の子は、
わたしの手をギュッと握ったあと、
帰り道を歩き出した。
わたしが女の子の背中にむかって、
「ありがと。そうだよね」
と言うと、女の子はふり返り
「よかった。来てよかった」
と言いながらニコニコと手を振った。
わたしはそのまま女の子と別れてしまうのが
惜しくなって、ふと
「お名前はなんていうの?」
と聞いてみた。
すると女の子は、自分の名前を答えて、
街の中に消えて行った。
「え。。。」
わたしはその名前に驚いた。
そういえば、あの子が着ていた服は、
昔の記憶をたどっていくと、見覚えがある。
「わたしも、あの服、着ていた。。。」
女の子がわたしに伝えた名前。
それはわたし自身の名前だった。
—
家に着くとわたしはペンを取り、
女の子にもらった折り紙の裏に
「サンタさんへ」
から始まる手紙を書き、
それを枕元にそっと置いた。
何年ぶりだろう。
靴下をベッドの横にぶら下げて、
こんなワクワクした気持ちで眠るのは。
「おやすみなさい。ありがとう」
次の朝、目覚めた枕元には
昨日ぶらさげた靴下があった。
その靴下は、少しふくらんで見えた。