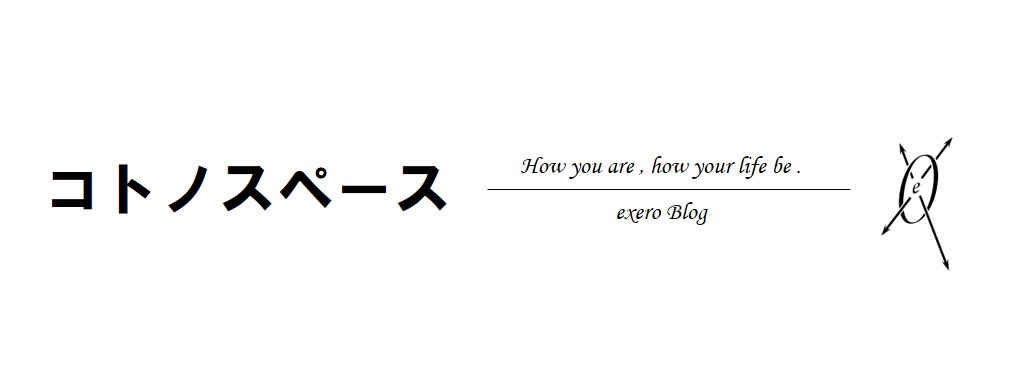最近、しばらく読まなかった文体に
あらためて触れている。
文芸書、小説、そういったジャンルのものだ。
個人的な話になるけれど、
昔々は、いろいろと小説を読んだ。
いわゆる「文豪」の作品も読んだし、
当時、多くの人から愛されていた小説も読んだ。
そこに踊る数々の美しい言葉。
表現の中で織りなされる物語にドキドキしたものだ。
そして、
「自分も、物語を書きたいなぁ」
なんて思って、いくつか書いていた時もあった。
しかし、社会人生活が続く中で、
「美しい文章」
よりも
「売れる文章」
が書ける方がいいのでは?と思うようになり、
一度、自分が憧れていた文体を自ら「壊す」ことにした。
セールスの文章は、文学作品とはまた違う。
「ですます」調と「である」調を
わざとミックスして使う時もある。
「そして、」と書いたあと、すぐに改行なんて、
それまでは信じられない!とも思っていたのだが、
そんな表現も多用する。
はじめは抵抗があったものの、
自分が後生大事に守っていた文体を壊すことによって
徐々にセールスの文章を書けるようになっていった。
そのおかげで、今では人の感情や欲望に
ダイレクトに訴えかける文章も
以前よりは書けるようになっていった。
そして、今。
なぜ今のタイミングなのかは分からないけれど、
大切な友人から
「この本、面白いよ」
と、美しい文体の小説を勧められて
何冊か読んでいる。
そこには、ずいぶん前にどこかに置いて来てしまった
日本語の美しさがつまっていた。
セールス文が書けるようになったことは
個人的には、ものすごい財産だ。
ただ、また以前のような文章も書いてみてもいいな、
なんてことも思ったりして。
そうはいっても、以前に書いていたものとは
また違うものになるだろうけれどね。
私としては、「わが家」から旅立って
「セールス文の冒険」をした後、
また「わが家」に帰還する気持ち。
「わが家」にいることには違いないんだけれど、
以前とはまったく違った経験をして、また書く。
そんな「ニュー・オールド」的な事も
やってみることができたら、面白いかなー
なんて思う次第。
(まぁ、そうは言っても、これからも
いつもの記事もじゃんじゃか書いていくけどね)
と、そんな風に思っていたら、
19年前に書いていたショートストーリーが
何篇か、ひょっこり出てきた。
「ああ、昔はこんなの書いていたんだなぁ」
と原点に戻るつもりで、今回そのうちの一篇を掲載するので
よかったら読んでみてくださいな。
改行以外は、当時のまま。ちょいハズカシイ(笑)
では、どうぞ~
—————————————————-
『Send off~届かぬふたり』
繰り返されるアナウンスの声。
急ぎ足で通り過ぎてゆく人々。
分厚いガラス窓の外には、白い機体を輝かせた飛行機が
整然と並び、翼を休めている。
英美は、その華奢な体には不似合いなほど
大きなトランクをカウンターに預けた後、
小さな溜息をひとつ吐いた。
「やっぱり、行くの、よそうかな・・・」
思い切ってあの人のところへ行ってみたところで、
一体何が変わるというのだろう。
あの人の心の中では、私は「過去の女」の一人にしか
過ぎないかも知れないのに。
今通ってきた通路を引き返せば、
またなんでもない普通の日々が待ってる。
つまらないけれど、あの人に振り回されることのない日々が。
あの人への想いは、時間が洗い流してくれる。きっと・・・
「あーっ、もっ、焦れったいわねぇ!!
いつまでウジウジ考えているつもり?」
英美が振り返ると、そこには白いセーラー服姿の少女が、
息を切らせながら額につたう汗を拭おうともせず立っていた。
「藍子・・・?」
英美は自分の目を疑った。何故ここに妹がいるのだろう。
「どうせ英美姉ちゃんのことだから、
ここまで来たって悩んでるだろうと思って、
このあたしが送り出しに来てあげたんじゃない。学校さぼって」
藍子は一気にまくしたてると、英美を見据えながら大股で近づいてきた。
そして大きく息を整えた後、自分の姉の顔を覗き込み、囁いた。
「行ってらっしゃい、英美姉ちゃん」
「留学、しようと思っている」
あの時の彼の一言は、今でもはっきりと胸に焼き付いてしまっている。
あの頃の英美は、自分が一番彼のことを知っていると思っていた。
彼のことで自分が知らないことなど、何もないとさえ考えていた。
しかし、それは間違っていた。
彼はあまりにも唐突に、英美に現実を見せつけた。
海外へ行くことを真剣に相談する彼の瞳は輝いていた。
英美にはそれがたまらなく悔しかった。
海外へ彼が行ってしまうことよりも「知らない彼」が、
自分の目の前にいることを認めたくなかったのかも知れない。
英美は彼の留学を喜んで見せた。
彼に「やめて」とは言えなかった。
すがる女とは思われたくなかった。
英美は彼の背中を押して、そして背中を見送った。
二年がたち、彼がいま何処で何をしているのかも
分からなくなってしまっていても、彼女の想いはさまよい、
ただよい続けていた。
会いたい。
会いたい。
もうそれ以上のことは考えられなくなっていた。
・・・でも。
「もう迷うのは、やめにしたんじゃないの?」
藍子が問いつめる。
「お兄ちゃんだったら、絶対英美姉ちゃんのことを
待ってくれているって。大丈夫だよ」
あの人のことは、妹の藍子もよく知っている。
家に遊びに来たこともある。三人で旅行に行ったりもした。
「あたし、英美姉ちゃんには、
お兄ちゃんと幸せになって欲しいの。
二人とも、あんなに仲よかったじゃない」
英美自身、藍子に言われなくともそんなことは分かっていた。
彼女の中で、すでに彼のもとへと旅立つ決心はついていた。
それでも彼女は黙っていた。
また迷いはじめてしまった自分を力づけてくれる言葉を、
もう少しだけ聞きたかった。
甘えていたかった。
うつむいたまま、英美は藍子に向かってつぶやいた。
「・・・こんな私でも、待っていてくれてるかな?」
この問いは、藍子への問いと言うよりも、
自分への甘えと別れを告げるための儀式だったのかも知れない。
藍子は間髪を入れずにこう言い放った。
「当然でしょ。だって、あたしのお姉ちゃんなんだから」
ゲートをくぐり、搭乗口へと向かう英美の晴れ晴れとした
後ろ姿を見送った後、雑多な飛行場から抜け出した藍子は、
澄みきった青い空をぼんやりと見上げた。
ひとすじの白い雲を描きながら、飛行機が太陽の下をかすめて行く。
「お姉ちゃん、幸せになるかなあ・・・?」
自動販売機でジュースを買う。
取り出し口にかがみ込みながら、藍子は呟いた。
「幸せに・・・ならないといいな」
ジュースを飲み干し、空き缶をくずかごへと放り投げる。
缶は乾いた音を立てて、くずかごへおさまった。
「ほんとはね、ほんとはね、英美姉ちゃん」
本当はあたしがあの人のところに行きたかったの。
本当は誰よりもあの人のところに行きたいのは、あたしなの。
英美姉ちゃんとあの人が一緒にいたとき、
あたしは何処にいればよかったの?
あの人の隣にいるのは、何でいつもお姉ちゃんだったの?
あたしじゃダメだったの?
「ばかだな・・・あたしって。
最後まで妹、演じちゃった」
夏が通り過ぎて行く。
昼下がりの木漏れ日は、いつまでもまぶしかった。
———————————————————-